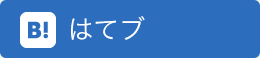森口祐子プロ・阿河徹プロのゴルフレッスン動画実践編
\ 読んで解る!ゴルフレッスン動画 / 明日から使える練習
大好評の「森口裕子プロ・阿河徹プロのゴルフレッスン動画」をそのまま記事ページにしました。
仕事の休憩時間や通勤の移動中にちょっと内容を見たいときや、ピンポイントでレッスン内容を確認したいときに最適です!
この「明日から使える練習」では、色々な球(バンカーショット、低い球、高い球、フックボール、スライスボール)を打つ練習、ダフリやトップを克服する練習、コースに出る前のチェックポイントなどを分かりやすくまとめております。
ぜひ参考にして下さい。

- 森口祐子プロ
- 1978年にプロ初優勝を飾り、そのあとはコンスタントに勝利数を重ね、2度の産休を経験しながらも通算41勝を挙げる。6名しかいないJLPGAツアー永久シード保持者の一人。

- 阿河徹プロ
- アメリカでスイング理論を学び、サンディエゴゴルフアカデミーを卒業。プロコーチとして谷原秀人プロや藤本佳則プロなどのスイング指導を行なう日本有数のトップコーチ。

実践編
練習場でできる!
バンカーショットの練習法
-

- 阿:
- 「ここではですね、バンカーショットが少し上手くなる、バンカーショットの練習方法を1点ご紹介したいと思います。
これはですね、バンカーの練習場の中で行なう練習方法なんですけれども、実際にボールは打たないでもできます。必要な物はバンカーレーキとサンドウェッジです。」
-

- 阿:
- 「まずですね、バンカーレーキでバンカーの中に直線を一本引いてみて下さい。」
-

- 阿:
- 「こんな感じですね。
と言う具合に直線を引いて頂いて、そしていつも使うサンドウェッジ、僕の場合は56度なんですけど、砂を打って練習していくんですけども、」
-

- 阿:
- 「この直線のこの線の上を含めて、線の上を含めてこの左側の砂ですね、こちら側の砂をスイングをして取って行ってあげると言う練習方法です。」
-

- 阿:
- 「これがこの線の右側を打ってしまう方が結構多いんですけれども、線の右側を打ってしまうと、想定以上にダフってってことになりますから、」
-

- 阿:
- 「これの大きな目的としては、クラブの最下点の位置のコントロールですとか、」
-

- 阿:
- 「もしくは、もうちょっとレベルを上げて砂を取る分量とか、砂の飛び方のコントロールって言うことに結びつく練習方法になります。
非常にバンカーショットのコントロールの能力が上がりますので、ぜひ一度バンカー練習場があるゴルフ場の中で練習してみて下さい。」
-

- 阿:
- 「何度かちょっとやってみますね。
こういった具合で砂の上を、この線の上を含めてて構いませんので取って行きます。」
-

- 阿:
- 「僕の場合、ボールを左足踵線上近辺に置くことが多いので、この場合も左足踵近辺に線を置いてあげて打って行く練習をやります。」
ポイントのまとめ
【練習場でできる! バンカーショットの練習法】
- バンカー練習場に線を引き(線上から)左側の砂を
スイングで取っていく - 右側を打つ→想定以上にダフッている
- 左足の踵辺りに線を置く
方向を意識して打つ練習
-

- 阿:
- 「ここではですね、コースに出る日の朝の練習場で、ぜひチェックをしておいて頂きたいポイントを一点紹介します。
それは非常に簡単なんですけど、ライン取り、方向取りですね。
方向取り、全然練習場でされていない方がかなり沢山いらっしゃいますので、これは必ず確認をして下さい。」
-

- 阿:
- 「練習場だとですね、マットがこういう風に正方形だったり長方形で形が作られていて、ここのマットもそうなんですけど、もう白いラインで方向が出ています。」
-

- 阿:
- 「ですので、後ろからライン上を確認して、マット通りにボールが飛んで行ったときに、何処にボールが飛んで行くのかということを、必ず後ろから確認しておいて下さい。」
-

- 阿:
- 「基本的にはそのラインに対して平行に打って行きます。目標取りをきっちり後ろから確認しておくと、ミスショットが出たときに何処にどの位曲がったのかっていうのが、自分で確認できます。」
-

- 阿:
- 「これを後ろから確認してないと、コースに行ったときに方向取りが全然取れなくなってしまいますので、非常に簡単な項目ではあるんですけど、後ろから確認して、目標を必ず設定して1球1球ボールを打つようにして下さい。」
ポイントのまとめ
【方向を意識して打つ練習】
- マット通り打つとどこにボールが飛ぶのかを後ろから
確認する - 目標を設定して1球1球打つ
ダフリ&トップを
克服する練習
-

- 阿:
- 「ここではですね、練習場でちょっとした工夫で、少し練習の内容をより効率よくしてあげる、ひとつ工夫を紹介したいと思います。
今ですね、7番アイアンを持っているんですけども、アイアンの練習をするときに、通常はアイアン用マットの上にボールを置いて、練習するんですけれども、結構ですね、大幅にダフったりトップをされる方、なかなかこう真ん中に当たらないという方、沢山いらっしゃると思います。」
-

- 阿:
- 「そんなときに、ドライバー用のティーがあります。ティーがありますので、ティーの上にボールを乗せて、ボールを打っていく。こういった練習をすることで、芯に当たる確率が非常に高くなります。
例えば僕ら、レッスンの現場で、インドアのレッスン場でしたら、テニスボールとかを良く使います。テニスボールを7番アイアンで打っていくと、意外にダフり・トップが、やっぱりボールが大きいですから出ないんですね。」
-

- 阿:
- 「それと同じ要領と言うか、少しティーアップをして、ティーアップをすることによって、やっぱりダフりとかトップはもう圧倒的に出にくくなりますから、このティーアップしたボールを打って行って、もしこれが例えば、自動ティーアップで高さを変えられるようでしたら、段々高さを低くして、そして最後はもう地面と殆ど同じ高さまで最後持っていって」
-

- 阿:
- 「そして、慣れて来て、感覚を掴んだあとに、マットの上に置いてあげて、そのマットの上のボールを打っていくと、比較的ダフりとかトップが出る回数が減って来ると思います。」
ポイントのまとめ
【ダフリ&トップを克服する練習】
- ティーアップして打つことで芯に当たる確率が高くなる
- 初めティーアップして打つ
慣れてきたら徐々に高さを下げていく
低い球の打ち方
-

- 阿:
- 「ここではですね、これ今7番アイアンなんですけど、ひとつのクラブを使って、球の高低、高い球と低い球の打ち分け方という所を紹介したいと思います。
コース内でも、林の中からのトラブルショットのときに、この技術を練習場で練習して習得しておくと、本番に非常に使えますので頑張ってやってみて下さい。」
-

- 阿:
- 「まずは低い球の方から行きます。
7番アイアンですと、通常の構えでしたら体のセンターよりもボール1個くらい左に置く方っていうのが多いと思います。」
-

- 阿:
- 「この場合ですね、低い球を打ちますので、クラブのロフト角を立てて、こういうロフト角で当ててあげる必要性が出てきます。
ですので球の位置はいつもよりは右側になります。」
-

- 阿:
- 「で、自分のこのセンターラインですね、ポロシャツのボタン、ベルトのバックル、あとズボンのファスナー、」
-

- 阿:
- 「このセンターラインより右側に置いて下さい。基本的に、右に置けば置くだけロフト角が立ってきますから、より低い球になります。
今日は2個分位は右に置いて打とうかなと思ってます。」
-

- 阿:
- 「グリップエンドの位置は、通常の左足の腿の内側、左内腿の所にセットして下さい。
そうするともう見て頂いて分かるように、ロフト角がかなり立ちます。多分5番か4番アイアンくらいのロフト角まで立ってると思います。」
-

- 阿:
- 「そして、体重位置は基本的には少し左に置いてあげます。
こうすることによって、立てたロフト角で、しかも左足体重でダウンブローに当てていけますから球をかなり低く抑えることができます。」
-

- 阿:
- 「あと技術的には、大振りしないで、この角度ですね、腕とシャフトのこの角度を、」
-

- 阿:
- 「リリースしてしまうと球が上がってしまいますので、リリースせずこの角度をずーっと保ったままフィニッシュまで打ち抜いてあげます。」
-

- 阿:
- 「こんな形のフィニッシュになりますね。そのポイントを気を付けて打っていってあげて下さい。
1球ちょっとチャレンジしてみますね。」
-

- 阿:
- 「ボール位置をセンターよりも今日は2個分くらい右に置いて、体重の位置は左に置きます。ロフトを立てたまま。」
-
-

- 阿:
- 「という感じで、低い球にチャレンジしてみて下さい。」
ポイントのまとめ【低い球の打ち方】
- 球位置は体のセンターラインより右
- グリップエンドは左の内ももにセット
- 体重位置は左
- 腕とシャフトの角度をフィニッシュまで保つ
高い球の打ち方
-

- 阿:
- 「では次はですね、先ほどと反対で高い球のコツをお教えしたいと思います。これも、林の中から木の上を超えてグリーンに届かせるのに非常に役立つので、ぜひ練習場で習得してみて下さい。
これも同じく番手は7番アイアンを使います。」
-

- 阿:
- 「高い球を打ちますので、フェイスを開くんですけど、あまりバンカーショットとか、グリーン周りのショットみたいには開けないです。そうしてしまうと、球が前に飛ばなくなってしまうので、全然グリーンに届かなくなってしまいます。なので、開く度合いは非常に少ない度合いですね。時計の針に見立てて言うと、30分位しか開けないですね。1時間も開けない感じになります。」
-

- 阿:
- 「そして球の位置、ボールの位置は先ほどと反対ですね。いつもよりもポジションは左になります。」
-

- 阿:
- 「左に置くことによって、インパクト時にこういう当て方ですね、要は、先ほどのロフトが立つ当て方と真反対で、こういうヘッドとグリップエンドの位置関係ですね。こうするとフェイスが上向きに当たりますから、ボールは上に高く上がっていきます。」
-

- 阿:
- 「高い球で攻めて行きますから、ボールも先ほどの低いのとは違って、少しスライス系のボールになりますので、足の向きもですね、こういう向き(右向き)というよりは、オープンスタンスって言うんですけど少し左向きの足の向きの取り方の方が打ちやすいと思います。」
-

- 阿:
- 「あと最後に、振り方のポイントは、先ほどここ(腕とシャフトのこの角度)をリリースしないでこの角度を保ったままって言ったんですけど、それも真反対になります。クラブを積極的に、リリースって言うんですけど、解いていってヘッドを先行させて、こういう動きですね、」
-

- 阿:
- 「手よりもヘッドが前にリリースされて、振り抜いていって、最後は高い振り抜きになっていきます。
低い振り抜きに持っていくと、球は低くなりますから、リリースをしながら、高い振り抜きでボールを出して頂きます。」
-
ポイントのまとめ【高い球の打ち方】
- クラブフェイスを少し開く
- 球位置は体のセンターラインより左
- 足の向きはややオープンスタンス(左向き)
- スイング時、手よりもヘッドが先行
- フィニッシュは高く振り抜く
フックボールの打ち方
-

- 阿:
- 「ここではですね、球を右左に曲げる練習、フック、スライスの練習方法、あとは習得方法をご紹介したいと思います。
これもコース内でトラブルになったとき、林の中に入ったりとか、前に木があるとか、そういったときに左右に曲げれる方法、技術を習得しておくと非常に役に立ちますので、練習場でぜひトライしてみて下さい。
また、クラブは7番アイアンを使ってやってみたいと思います。」
-

- 阿:
- 「まずはフックボール。右打ちですので、右から左ですね。フックボールのコツ、習得方法を説明します。
まず、ボールは左回転ですね。左に回転をかけますので、クラブフェイスの向きはこういうまっすぐな状態よりも、被せていきます。」
-

- 阿:
- 「被せる度合いが大きくなればなるだけ、左回転のフックの度合いも大きくなります。
今ここではですね、1時間くらいですかね、1時間くらい被せたフックフェイス、シャットフェイスになった状態をやってみたいと思います。」
-

- 阿:
- 「まず、打ち出したい方向。マットの向きじゃなくてもっと右ですね。自分が打ち出したい方向に対して、まず体の向きはセットしてあげて下さい。
で、それに対してフェイスが被ってますから、およそクラブフェイスの向きは、最終目的地点の辺りですね。この練習場だと、あの250とかですかね。あの辺りの方向に、クラブフェイスは向いていきます。」
-

- 阿:
- 「クラブを振っていく軌道の方向は、自分の体の方向、もしくは打ち出したい方向ですね。
この方向と重なっていきますから、軌道はこちらの方向、目標よりも右に振ってます。その軌道に対して、クラブが被ってますから、ボールは左回転がかかっていきます。
まずこのポイントだけ、一番簡単なポイント、ここを押さえて、練習場で打ってみて下さい。
実践してみます。」
-
ポイントのまとめ【フックボールの打ち方】
- クラブフェイスを少し被せる
- ファイスをかぶせるほどフックが大きくなる
- 打ち出したい方向を目標の右側に設定
- クラブの軌道と打ち出したい方向が重なる
スライスボールの打ち方
-

- 阿:
- 「では、スライスの打ち方。右打ちなので、左から右ですね。左から右へ球を曲げるコツ、方法をお教えします。
これもトラブルショットのとき非常に役に立つので、ぜひ頑張って習得して下さい。」
-

- 阿:
- 「こちらはですね、球を左から右へ、右回転がかかるようにしますので、まずクラブは、まっすぐよりも開きます。こちらの方向ですね、これも開けば開くだけですね、やはり右回転かかるんですけど、」
-

- 阿:
- 「こういう風に開いて行けば行くだけですね、下に下ろしたときに、ロフト角が同時に上を向いてきます。なのでボールが全然飛ばなくなってしまうんですね。前方へ出る、前に直進する力が減ってきてしまいますので。」
-

- 阿:
- 「やはりこれもまずは、30分から1時間未満で開く分量の中で、練習してもらうのが一番良いと思います。これ以上開くと、かなりヘッドスピードが速くないと、球が前方に飛んで行かないですから。で、これを開くこと、これをまず習得することですね。」
-

- 阿:
- 「そして、打ち出したい方向、フックボールとは逆で、目標の左側に設定します。
左から右へ球を曲げていきますから、練習場で後ろから確認をして、例えば、250が最終目的地点だとして、それよりも左側に、」
-

- 阿:
- 「15ヤードから20ヤードくらい左側に打ち出したい、出だしの方向を設定します。
そこに対して体を向けていきます。
こういう向きになりますかね。」
-

- 阿:
- 「そして原理としては、フックボール・スライスボールは反対なんですけど原理としては同じで、振っていく軌道はこの軌道です。」
-

- 阿:
- 「この軌道に対して、やはりフェイスの向きが、軌道に対して結果的に合ってないです。軌道に対してフェイスは開いてますから、球に右回転がかかって、左から右へ曲がっていくという、そういう原理、メカニズムになります。」
-
ポイントのまとめ
【スライスボールの打ち方】
- クラブフェイスは少し開く
- フェイスを開くほど球は飛ばなくなる
- 打ち出したい方向を目標の左側に設定
- 打ち出したい出だしの方向に体を合わせる
練習場でできる
深いラフの打ち方練習
-

- 阿:
- 「ここでは、深いラフからのアプローチを向上させるための練習方法をご紹介したいと思います。
実際、練習場のマットですので、ゴルフ場の深いラフと全く同じシチュエーションとかフィーリングって訳にはいかないんですけれども、ゴルフ場の深いラフで打つときって言うのは、大抵の場合フェイスを開いて打つことが多くなります。フェイスを被せて打つ場合も稀にあるんですけど、大体の場合は開いて打つケースが増えます。」
-

- 阿:
- 「ですので、練習場でフェイスを開いて、開いたフェイスで打っていくっていうことに慣れておいて頂きたいです。
芝の抵抗とかは練習場なんで全然ないんですけど、これが普段開くことに慣れてないと、なかなかコースに出ていきなり開いて下さいって言われても全然開けないので、練習場の段階で、開く練習というものをぜひやって下さい。」
-

- 阿:
- 「このときに、開き方にポイントがあります。
僕らが開くときに必ずやるのは、クラブを開いて、例えば1時間、2時間開いてからグリップを握っていきます。
つまり、もうすでに開いてあるクラブに対して、グリップをいつものように作っていくんですけど、」
-

- 阿:
- 「結構ですね、アマチュアの方の、開くことに慣れていない方っていうのは、いつもの構えで、腕をねじって開くんですね。」
-

- 阿:
- 「で、こうしてしまうとですね、確かに一見開いているように見えるんですけど、インパクトのときには、いつものインパクトの形に戻ってしまいますから、全く開いていないのと同じことになってしまいます。ただ歪めているだけ。」
-

- 阿:
- 「それを、開いたクラブを握るっていう風にすると、インパクトのときにも開いて戻って来ますから、いつもよりもロフト角が多い状態で戻って来ます。
これは深いラフからボールを脱出させるのに非常に役に立ちます。」
-

- 阿:
- 「もうひとつですね、こういうサンドウェッジとか、ロフト角の多いクラブはですね、フェイスの左右の向きに対して、非常に特性を持っていて、」
-

- 阿:
- 「練習用のゴムティーをちょっと利用させて貰うんですけど、練習場のゴムティーに両面テープをくっ付けているだけです。こうやってやると、フェイスにゴムティーがくっ付きますから、フェイスの向きを立体的に、少し見やすくなります。
棒が長いともっと見やすいんですけどね。」
-

- 阿:
- 「これを下に置いて、被せていきます、こうやって、フックフェイス・左向きに被せていきます。そうするとフェイスが被ります。つまり、目標に対して左向きになります。」
-

- 阿:
- 「で、フェイスを開いていきます。開いていくと、右向きじゃなくて上向きになるんですね。
こっち(被せると)は左に向くんですけど、こっちは(開くと)上に向きます。
つまり、ロフト角の多いクラブ、サンドウェッジとか、アプローチウェッジとか、そういう物は、開けば開くだけ上に向きますので、」
-

- 阿:
- 「ボールの飛び出していく方向を最終的に決定付けるのは軌道になります。
軌道が例えば、こちら(インサイド)からこうやって振ったら右に飛びますけど、通常通りの軌道だったり、もしくは若干アウトサイドから入れてきたりってすると、右に飛び出すことはまずないので、ご心配なくっていう所ですね。」
ポイントのまとめ
【練習場でできる深いラフの打ち方練習】
- クラブフェイスを開いた状態で打つことに練習場で
慣れておく - フェイスを開いた状態でグリップを握る
- ロフト角が多いクラブは開けば開くほどフェイスは
上を向く
コースに出る前
気を付ける点
-

- 阿:
- 「ここではですね、コースのスタート前の練習で気を付けて欲しいチェックポイントというか、気を付けて欲しい点を一点ご紹介したいと思います。
僕らもコースで回るスタート前に、気を付けることの一番重要なポイントに、リズムと力感というのがあります。」
-

- 阿:
- 「スイングを、クラブを振っていく力加減と、あとリズムですね。ここに最後は気を付けて、実際に練習に取り組みます。
練習場とかコース内でも気を付けるのは、このリズム。自分なりのリズムでいいんですけど、1、2の3、このリズムですね。これを気を付けて、練習もコースもやっていきます。」
-

- 阿:
- 「そうするとですね、僕の場合なんかもそうなんですけど、コース内でリズムを気を付けてやっていると、段々段々結果的にインパクトのタイミングが、ホールを重ねるごとに合ってきて、意外に曲がり幅が小さくなってきたりとか、比較的起きることが多いです。」
-

- 阿:
- 「ですので、アマチュアの方も、1、2の3というこのリズム感ですね、ここを特にコースを回る直前は、非常に重要なポイントにおいて練習とコース内でやってみて下さい。」
ポイントのまとめ
【コースに出る前 気を付ける点】
- ショットのリズムに気を付ける
→ホールを重ねるタイミングが合ってくる
スタート前に練習場に
持っていくクラブ
-

- 阿:
- 「練習場に持ってくるクラブのパターンですね。ここをご説明したいと思います。
今ですね、5本を今日は練習場の方に持ってきているんですけれども、1本だけ持って来るという方、たまに見かけます。
特に、ドライバーだけ持って来るっていう方もいらっしゃるんですけど、これはもう、まず僕たちプロゴルファーとかインストラクターとか、まずやらないです。」
-

- 阿:
- 「コース出る前は、最低でもこういった感じの5本、今日は56度のサンドウェッジ、6番アイアン、ユーティリティ一1本、フェアウェイウッド、ドライバーっていう風に、こう見て頂くと長さが違うんですけども、こういった感じで番手が違うものを、必ず5本から6・7本は持って行きます。」
-

- 阿:
- 「そして、それぞれ下の番手から、この場合ですと56度のサンドウェッジから練習をして行って、朝なのでなかなか体が動かないので、小さい番手から練習をして行って、段々上の大きい番手に流れを作って行ってあげます。」
-

- 阿:
- 「小さい番手の方が、小さい動きの中で、力感もそんなにない状態で打てますので、小さい番手から必ず練習をして下さい。」
-

- 阿:
- 「あとはですね、長さがこれだけ違いますから、アドレスの位置だったり、スタンスの幅だったり、ボールポジションがかなり変動してきます。」
-

- 阿:
- 「例えばですね、今日はこんな感じで2つ並べて説明できるので、長さを具体的に見て頂きたいんですけど、ここにボールが、ちょっとティーアップがないですけどボールがあって、例えばドライバーだと、僕のスタンスの場合でここですね。
ボールの位置は左足踵線上くらいで。ボールと自分の体の距離が、僕のアドレスでここになります。
-

- 阿:
- 「これに対して、56度のサンドウェッジを同じスタンスの位置で持ち替えるとすると、スタンス幅狭くなるので、右足を寄せて行きます。」
-

- 阿:
- 「そして、ちょうどここですね。手の位置もここで。ボールは手前に寄せたいんですけれども。
ドライバーとの位置関係にこのぐらいの誤差が出てきます。」
-

- 阿:
- 「クラブが変わると、ボール位置、あとスタンスの構え方にだいぶ変更が出てきますので、特にですね、1週間とか2週間ゴルフができなかったっていう方だと、ひとつの番手でずっと練習してると、なかなか対応ができないですので、」
-

- 阿:
- 「必ず、複数、5本、6本、7本持ってきて、アドレスの位置のチェックをしながら、朝の練習をやって下さい。」
ポイントのまとめ
【スタート前に練習場に持っていくクラブ】
- 練習場に長さの違うクラブを5~7本持っていく
- 短いクラブから順に振っていく
- 長さの違うクラブで構え方とボール位置を確認する